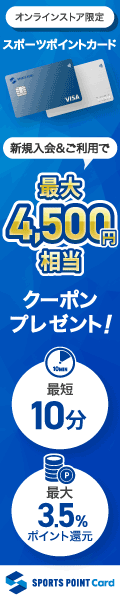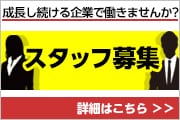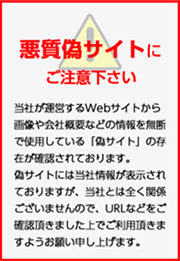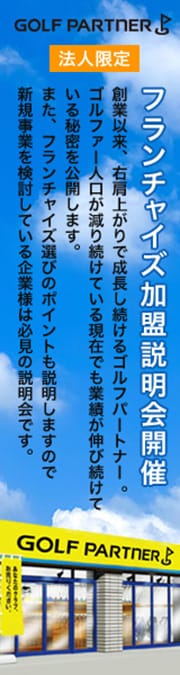普通、飛ばし屋ほどフェアウェイキープ率は低くなる。反対にフェアウェイキープ率が高い曲がらない選手ほど平均飛距離は低くなるもの。飛ばすか曲げないか。どちらかが突出していれば、片方は下がる。しかし、蝉川泰果(せみかわ・たいが)は「日本オープン」で驚異的な数字をマークする。ドライビングディスタンスは309.125ヤードで2位、フェアウェイキープ率は73.214%で4位と、文字通り飛んで曲がらないドライバーで優勝したのだ。
ドライバーの総合力を示す『トータルドライビング』という部門がある。ドライビングディスタンスの順位とフェアウェイキープ率の順位を合算したものだ。石川遼は「めちゃくちゃドライバーが上手い印象で、トータルドライビングは彼のためにあるみたいな感じ」と驚嘆する。そんな蝉川のスイングは一見するとクセが強くて個性的。カタチだけを見ると、飛んで曲がらないとは信じがたいのだ。小・中・高と蝉川を教えてきた青木翔氏に、飛距離と正確性を両立する要素を聞いてみた。
「クセだらけですよね」と青木氏。蝉川のグリップを見ると、左手を上からかぶせて握る強烈なフックグリップ。そしてトップではシャフトが飛球線とクロスする。フックグリップはまだしも、シャフトクロスはスイングプレーンから外れる動きであり、下ろすときにうまく戻せないと曲がる原因にもつながる。
「フックグリップ(からの変更)はショットに悩んだときに一回チャレンジはしました。もうちょっとスクエアにしたけど、やっぱり無理だった。シャフトクロスに関しては、それで泰果が困っていなかったし、自分の体の特徴に合わない無理なことはやらずに、他のことをやればいいと思って直しませんでした」と話す。
さらに、「体重移動もできなかった。正面からバックスイングを見ると、右腰がアドレスの位置よりも中に入ってくる。移動はしていないんです。体重移動できないのなら、回転力を使えばいい」と、体の特徴に合わせて型にはめることはしなかった。スイングは青木氏が教え始めた小学校6年生の頃と「ほとんど変わっていない」という。
その曲がらない要素は「フェースローテーションが少ないこと」。フックグリップで握った時点でフェースはつかまる準備ができている。ひと昔前は、体の前でフェースを返し、いわゆる“さばく”動作でボールを飛ばしていた。しかし、現代のドライバーはフェースローテーションが少なくても飛ぶ。ローテーションを使うとかえってフェースが戻らずに右プッシュを招くのだ。
「インパクト直後を見ても、手首のカタチを変えずにそのまま押し込んでいる。僕ら昭和の人間から見ると、クラブをさばく動作が少なくてフォローで手首の角度が浅い。僕らはもっと角度がついていた。そこが泰果たち新世代の子たちですよね」。そう青木氏がいうのはインパクト後のクラブの動き。普通は左ヒジがたたまれて腕とシャフトの角度がついていくが、腕とクラブが一本の棒のように動き続ける。手首の角度が浅いままキープされているのだ。当然フェースが真っすぐ動く時間も長くなる。
さらに青木氏は、インパクトのお尻のカタチにも曲がらない要素があるという。「これだけボディターンの感じでスイングしていて、胸がしっかり回って上半身の運動量がしっかり出ている。だから、後ろから見てインパクトのときに左のお尻があまり見えない」という。どういうことなのだろうか?
「ゴルフのスイングの力学的なところでいうと、一番運動量が多いのはクラブ。手があって肩、お腹って運動量が下がっていくわけなんです。だからちゃんと上が追い越しているんです。女子だとインパクトのときにもっと左のお尻が見える。泰果は無理に体を回して振り遅れてっていうスイングじゃないから、タイミングとかを気にせずにバーンと振れば曲がらない。逆に体が行きすぎてしまう選手だと、インパクトで一回待って合わせる動作になるんですよね」。つまり、下半身が先行しすぎないから、タイミングもズレにくいというわけだ。
では、飛ばしの要素は? 「単純に自分の馬力で飛ばしています。回転力と足の蹴りですね。地面反力です」。蝉川のインパクトを後方から見ると、クラブと引っ張り合うように後ろに飛んでいる。その証拠にインパクト以降は特に左足の位置が後方に下がる。PGAツアーの飛ばし屋、ジャスティン・トーマス(米国)の飛ばし方に近いかもしれない。「確かに下がっていますね。僕なら当たらないです」と青木氏は笑う。
フェースローテーションを抑えた曲がらない車体に、最大ヘッドスピード56m/sのエンジンを積んだ蝉川のスイング。振れば振っただけ飛距離が出る現代ドライバーの申し子といえるかもしれない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>