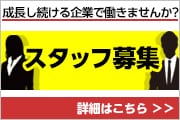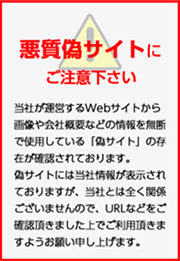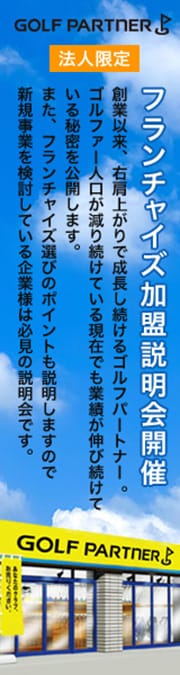国とはなんだろう。それぞれが勝手に利益を追求する、くだらない縄張り意識に過ぎないのではないか? 貿易摩擦から宗教の対立、戦争に至るまでのあらゆる争いは、利害のぶつかり合いが個人レベルから徒党を組んだ集団レベルになっているだけのこと。集団が“会社”、“国家”と大きくなっていけばいくほど争いはどんどん正当化され“国益”という名になると、時に正論すら握りつぶすほど大きくなる危険をはらんでいる。
世界でも戦える二人 渋野日向子と鈴木愛の貴重な2ショット【写真】
ゴルフという小さな世界の中でも同様だ。男子なら米ツアー、欧州ツアー、アジアンツアー、日本ツアー、オーストラリアンツアー、南アフリカツアーなどの地域によるものもあれば、同じエリアでファンやスポンサーを奪い合うこともある。選手があちこちを渡り歩くのが当たり前になったころから、お互いが話し合い、ワールドランキングという共通の基準を作ったり、歩み寄ったりを進めている。欧州ツアーがアジアンツアーとの共催大会を行い、米ツアーがアジアに進出したりする動きもあり、様々な思惑が入り乱れているのが現状だ。
女子はどうか。米国、欧州、日本、豪州、韓国、中国、台湾など各地でツアーが行われており、最強といわれる米ツアーに対し、日本は人気という点では勢いがある。強い選手ほど海外に流出してしまう傾向にある韓国、ゴルフ発祥の地の誇りを持ちつつも、苦難の道を歩いてきた欧州、一気に広がりを見せようという動きのある中国などが、それぞれ別の動きをしてきた。お互い、話し合いの場がなかったわけではない。ロレックスが冠に着いた世界ランキングを、メジャー出場権などに反映させるのも男子に右へならえ。それでも、さまざまな面でともに歩んできたとは今ひとついえなかった。昨年までは。
だが、昨年9月に欧州女子ツアー(LET)は、米国女子ツアー(USLPGA)と手を組むことを決断。その効果が、先週、発表された2020年欧州女子ツアーのスケジュールに表れている。24試合中15試合が欧州で行われ、残る9試合は豪州、南アフリカ、サウジアラビア、タイ、インド、UAE、ケニヤ、などさまざまな場所での開催となり、8月の東京五輪もカウントされている。
賞金総額はツアー史上最高の18万ユーロ(約21億6000万円)。対等な関係というよりも、欧州ツアーの上位選手が、米ツアー出場権を得るという下部ツアーのような形態ではある。だが、海外進出を積極的に行いたい米国と、ツアー存続に苦労する欧州の利害が一致した形。うまく進めば、米国以外の選手は自国と米ツアー両方でのプレーがしやすくなり、選手層はさらに厚くなる。プロツアーの底辺が拡大されることにつながるはずだ。
アジア進出にも拍車がかかり、韓国や中国ツアーと結びつく機会も増えるに違いない。では、日本はどうするか。現在、国内ツアーだけで試合数、賞金ともに十分ではあるが、制度が変わったことでそこでプレーできない選手を中心に、中国など海外に活躍の場を求める者も増えている。「ステップ・アップ・ツアーを海外で開催することも考えている」と、昨年末、JLPGAの小林浩美会長は話していたが、今のところまだ具体化したという話は聞こえてこない。
米国、欧州両ツアーのアジア進出からの世界女子ツアーの大きな流れは、ボーダーレスへと続いて行くのか。日本だけで試合ができているからといって、それがずっと続く保証はどこにもなく、現実として力のある者は米国に戦いの場を求める傾向にある。
ゴルフだけでなく、さまざまな面で世界は確実に“狭く”なっている。インターネットが一般に普及してからすでに四半世紀以上が経ち、スマートフォンで世界のどこにいても繋がることができる時代。一瞬にして情報がどこにいても得られる今、地域や国などに縛られる必要などないのかもしれない。出身地域を大切にする気持ちは持ち続けたいが、そこにこだわるあまり排他的になることにはあまり意味がない。選手の“足かせ”になり、取り残される要因になる危険もはらんでいる。
足元をしっかり見つめつつ、自分たちのことだけでなく、大きな目での発展を考える。プロツアーだけでなく、ゴルフそのものの普及がそのベースにあるのはいうまでもない。欧州ツアーのスケジュールを見て、その必要性を改めて思う。(文・小川淳子)
<ゴルフ情報ALBA.Net>